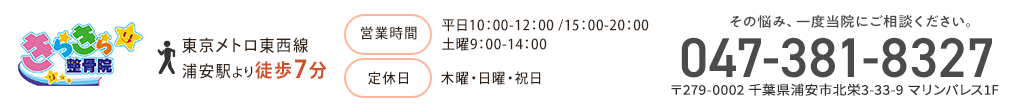小説「掌の記憶」終章
エピローグ
モデル都市のようだった街は、今はどことなく旧時代を感じさせる。
人の手による復旧の証は、舗装の歪みや色の違いすら芸術作品の「味」のように温かい雰囲気を醸していた。
遊歩道には、家族連れやペットを連れた住人たちが戻り、風に揺れる樹木の葉も、傷跡をそっと包んでいるかのようだった。
その街並みの一角で、灯る看板があった。
「きらきら整骨院」
そこにあるのが当たり前だった小さな看板は、今は希望の道標のように輝いていた。
扉を開けると、穏やかな空気と、安心感のある笑顔のスタッフたちが出迎えてくれる。
ゆぅさんは、予約帳をめくっていた。
「今日は、サポートが必要な患者さん2人いるから、よろしくね」
僕が奥から声をかけると、彼女は顔を上げ、笑って答えた。
「大丈夫。今日はちゃんと〈ゆぅ〉だから」
AI接続の後遺症らしく、時折うわの空でぼんやりとすることがあった。
そんな時は、決まって難しい案件の解決策なんかを思いつくらしく、彼女はそれを〈YOU状態〉と呼んでいた。
彼女自身に混在している何かを敵とは考えずに、受け入れた結果なのだろう。
この街の再生とともに、彼女もゆっくりと新たな自分を作り始めているのかもしれない。
扉の外では、風鈴の音が鳴っている。
夏の始まりの音だった。
──大深度地下。
第六中央制御局 管理調整ブロック。
AI調整官たちが詰める、無窓の管制室には、規則的な電子音が反響していた。
重たい自動扉が閉まり、人工光に満たされたフロアに、軽やかな足音が響く。
「石井様、報告書をお持ちしました」
「お、雪野ちゃんか」
声の主は、ゆったりとした仕草で椅子を回転させた。
無造作だが無駄のない雰囲気をまとう男。報告書にざっと目を通して、口元をふっと歪める。
「今回は、まさかの笹本ちゃんにやられちゃったよねぇ…」
「良い所に当てたんだけどなぁ」
と言って、指で銃を撃つ仕草をする。
「治療院の二人はどうしますか?」
「今もアクションは無いだろ?あっちも身バレしたら、色々と困るはずだし。ダンマリを決め込むなら、放っておくさ」
「了解しました」
「あ、でもまた治療には行っておいでよ。現場感、忘れないようにね」
雪野は視線を伏せ、静かにうなずいた。
ー室内アナウンスが響く。
『石井慎也統括官、局長室にお願いします』
するりと彼は立ち上がり、ネクタイを締め直しすと、背後のモニターに目をやりながら、つぶやいた。
「今度こそ、君がターゲットだよ。オカバ」
瞳には、好奇心と悪戯心に満ちた光が揺れていた。
(完)