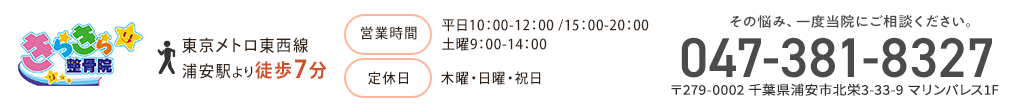小説「掌の記憶」第二章
― 交差する眼差し
今朝は、いつもより早く治療院に来ていた。
お祭りの煽りなのか、予約帳はびっしりと埋まり、開院前にもかかわらず、数人の患者が並んでいた。
僕は、受付から治療室を一瞥する。
「先生、朝からすごい活気ですね~」
ゆぅさんが明るく言いながら、バインダーを手渡してくる。
「なんだかね。でも…なんか違うんだよなぁ。活気というより…浮ついてる?みたいな」
「うん。わかる気がする」
ゆぅさんは小さく頷き、待合室の方に視線を向けた。
患者たちはそれぞれ穏やかに談笑していたが、話している内容が、どれも同じような内容だった。
「昨日のフェスティバル、すごかったね」
「なんか眠りの質が全然違うんですよ」
「朝起きたとき、身体が軽くて…これはもう、革命的っていうか…」
皆が口を揃えて「よく眠れた」「身体が軽い」「癒された」と話している。
どんなに調子がいい時でも、必ず不満を話す人ですら、疑問一つ持たずにそう話している。
それどころか、顔つきまでどこか柔らかくなっていた。
──まるで、何かを手放してしまったような目で。
一人目、二人目と施術を終えるごとに、不安は強くなっていった。
どの人も、表面上はすこぶる快適そうだ。
しかし、その調子がいいという自覚と、実際の体調がまったくリンクしていない。
その調子の良さは、なにかを上書きしてしまっている感覚に思えた。
そもそも、本当に楽であるのならば、ここに来る必要も無いのだから。
___何も感じさせないことへの違和感
その奇妙な感覚に戸惑う人々が、今ここに集まって来ているのだろう。
◆
陽が傾き始めたころ、ドアチャイムが鳴って、扉が開いた。
「こんにちは。予約していた雪野です」 柔らかい声と共に現れた女性――
以前は「甘中」と名乗っていた旧知の患者だった。
事情があるのだろう。僕は何も問わなかった。
雪野は、グレイのシャツに黒のパンツというシンプルな服装で、化粧も控えめだったが、どこか研ぎ澄まされた雰囲気をまとっていた。
「久しぶりですね。お変わりなさそうで、安心しました」
「先生こそ、お元気そうで」
互いに小さく笑い合いながら、施術室へと入っていく。
ベッドに横たわった雪野さんは、ぽつりと呟いた。
「そういえば…今年のお祭り、明らかに違いますね」
「やっぱり、そう思いますか」
「ええ。音、香り、光の配置、人の動線までが完璧に計算されてる」
「感覚の順番までコントロールされた体験設計。まるで…誰かが実験してるみたい」
雪野さんは天井を見つめたまま、口元だけを動かした。
◆
⸻
仰向けになった雪野の頬には、微かな緊張があった。
彼女はそれを隠すように、目を閉じていた。
首の状態を丁寧に確認する。
「結構、張ってますね。呼吸、浅くなってるの気づいてました?」
「ええ。寝ても疲れが抜けない感じでした。なのに、身体は軽いって錯覚してる」
「錯覚?」
「軽さというより、麻痺に近い。不調に気づかなくなってる?というか…」
その言葉は、彼自身が朝から感じていた違和感に、見事に合致していた。
(上書きされた快適さ)
彼女の頚椎に軽く指を添え、そこから胸郭、腹部へと繋がる全身の張りを読むように圧をかけていく。
「…っ」
雪野の喉元が、びくりと震えた。
今の反応は、明らかに通常の痛みやコリの反応とは異なる。
もっと、深い部分での“拒否”。
筋肉でも神経でもない領域が“触れられた”ような反応だった。
「大丈夫ですか?」
「ごめんなさい、平気です。でも今、一瞬…頭の奥に、変な映像が…」
「映像?」
「光が降ってくる感じでした。天井じゃなくて…目の内側にゆっくりと」
僕は直感で確信した──ただの施術ではおよばない。
「雪野さん、ちょっと体勢を変えましょう。うつ伏せになれますか?」
彼女は頷き、ゆっくりと体を動かした。
彼女の背中に手を添えたとき、ごく微細な“違うリズム”が脈打っていた。
まるで彼女の中に、もうひとつ心音が宿っているような──
「先生、もし……この街で何かあったら、私を信じてくれますか?」
そう呟いた彼女の言葉の奥には、明らかに覚悟が込められていた。
◆
施術を終えたとき、彼女は深く息を吐いた。
「この感覚。久しぶりです。自分が戻ってきた気がします」
「そう言ってもらえると、こちらも救われますよ」
笑い合う二人の間には、静かな緊張が漂ったまま、雪野さんは帰っていった。
院のドアが閉まったあと、じっと手のひらを見つめた。
──そこに触れた存在はいったい何だったのだろう。
◆
夜の広場は、静かだった。
それは「人がいない」という意味ではない。 むしろ、人の数は多い。
笑い声も、音楽も、店の呼び込みも聞こえる。
だが、そのすべてがどこか抑制され、整然としすぎていた。
診療を終えたあと、ひとり街へ出ていた。
目的はなかった。ただ、じっとしていられなかった。
――風が吹く。涼しくて、心地よいはずの夜風。
しかし、それすらも人工的な温度と湿度の空調みたいに、どこか作為を感じさせた。
広場を囲む遊歩道沿いには、昼間見かけたプレハブ店舗がさらに増えていた。
それぞれのブースには、ネオンのような光が浮かび、カラフルな色彩で通行人を誘っている。
香りが漂う。 甘く、スパイシーで、どこか懐かしい――
人によって香りが異なるのだろうか。
前を歩く女性は、花のような香りに立ち止まり、目を閉じて深く息を吸っていた。
屋台に目を向ければ、昔ながらの綿菓子やたこ焼きに似た見た目の食品もある。
けれど、パッケージや調理器具はあまりにも未来的で、誰が作っているのかも、はっきりとはわからない。
少し離れた場所では、子どもたちが「光の輪投げ」や「思考反応型スロット」と題されたゲームに興じている。
明るさはあるのに、街は妙に音を立てない。
笑い声はあるのに、誰かと目が合わない。
立ち止まり、遊歩道の先を見やった。
新たに設置された巨大なドーム型の建物が、白く光を放っていた。
その周囲に集まる人々は、陶酔したような表情で、静かに何かを見つめている。
「まるで、祈ってるみたいだな」 そう呟いたときだった。
すぐ近くのベンチに腰掛けているひとりの男に、視線が吸い寄せられた。
◆
「……あれ、岡林じゃないか?」
ふと顔を上げた男の声に、僕は一瞬だけ心が和らぐのを感じた。
変わらない、穏やかで芯のある声。
懐かしさと同時に、その奥に微かな翳りを感じとっていた。
「慎也…?」
歩み寄った僕に、彼は少し笑って言った。
「どうしたんだ【オカバ】そんな顔して。元気にしてたかい?」
「ああ、久々にそのあだ名で呼ばれたよ。…懐かしいね」
「僕は、このあだ名しかしらないからな」
慎也は、スケッチブックを広げたままベンチに腰を下ろしていた。
その紙面には、この街の広場が描かれていた。
だが――そこにあるのは、今の風景とは違う。
人の姿がある。木陰がある。自然なざわめきがある。
「……これ、いつ描いたの?」
「去年のフェスティバルの時だよ。静かで、気持ちのいい朝だったなあ」
「今年は…妙な建物ばかりだよ」僕が呟くと、彼はゆっくり頷いた。
「確かに、去年まではちゃんと祭だった…今は、実験に近い気がするんだ」
「やっぱり、そう感じるよね」
慎也は、スケッチブックを閉じて空を見上げた。
夜空は澄んでいたが、どこか遠くから人工的な光が滲んでいた。
「人の斜め上を行くこの発想力はおそらくAI思考なのだろうけど」
「でも、使っているのは結局人間だよ―それも少し怖いと思わないか?」
言葉を失い、僕たちはしばらく無言でいた。
近くでは誰かが笑っていたが、その音もどこか遠く感じられた。
「…まだ僕は、自分が正気だと思ってる」 慎也はふいに言った。
「ドームに入った人の顔を見たことがあるかい?」
「あの中に?」
「うん。目の色や表情が、なんて言うか曖昧になってる感じ…喜びでも驚きでも安堵でもなくて空っぽなんだけど、満たされているような」
慎也の手が、ほんのわずかに震えていた。
僕は、何も言えずその手を見つめた。
「なあ、オカバ」 彼はやわらかく微笑んだ。
「君って背負いすぎるところ、昔から変わってないよな。そういうところが、心配なんだ。何でも一人でなんとかしようとする」
「僕は……」 そんなことはないよと返事しようとして口ごもる。
「大丈夫。僕は、まだ君の味方だよ」
その言葉の余韻が、夜の静けさの中で深く沈んでいくようだった。
也は立ち上がり、スケッチブックを小脇に抱えた。
「また話そう。ちゃんと、ゆっくり」
そう言って彼は、静かに広場の灯りの中へと歩き出した。
その背中に、僕は声をかけなかった。
なぜか、呼び止めてはいけないような気がしたのだ。
淡い光が遊歩道に揺れていた。だが、その灯りの色合いは、かつてこの街を包んでいた“やさしい明るさ”とは明らかに違っていた。
――僕は、正気でいられているのだろうか?
気づかぬうちに、あらゆるものが静かに書き換えられている。
記憶も、感情も、常識すらも。
──それが、いまこの街で起きている“治療”なのだとしたら。
「……戻ろう」
◆
院の扉を閉めると、空気はひときわ静かだった。
時計の針は午後11時を回っている。
診療はとうに終えているはずなのに、身体はまだ休息を受け入れていない。
ふと、カルテ棚の一番上に目が留まる。
そこには雪野さんのファイルがあった。
今日、彼女が口にした言葉が胸の奥で静かに反響する。
「……この街で何かあったら、私を信じてくれますか?」
彼女はすでに、何かを見ていた。
この街を、あるいは、これから失われていく本質を。
僕は椅子に腰を下ろし、深く息を吐いた。
やがて、ほんのわずかな機械音が院内に響いた。
ドアチャイムではない。もっと静かに、意図的に紛れ込んでくるような──電子音。
受付のカウンター越しに、小柄な女性が立っていた。
白衣でもスーツでもない。
明るく整ったカジュアルな服装。
誰かの紹介で来た新しい患者かとも思えるほど自然な雰囲気だった。
だが、彼女の目は違った。笑っていたが、笑っていなかった。
その奥には、何かを測るような静かな光があった。
「こんばんは。突然のご訪問、申し訳ありません。……少しお時間いただけますか?」
「こんな深夜に?体調の相談ではないですよね」
警戒した強い口調で言葉を返す。
彼女は名刺を差し出した。そこには、簡素なロゴと共に、こう記されていた。
AI医療調整官(コンサルタント)──笹本 理那
「街の新しい取り組みについて、個別にご説明をしていまして。とくに先生のような方には…ご協力をお願いできればと」
その穏やかな声色の背後にある<なにか別の力>は、すでに院内にまで入り込んでいる気配を帯びていた。
名刺を受け取ったまま、僕はしばらく言葉を失っていた。
この訪問は、いずれにしても非常識ですぐにでも追い返すべきなはずだ。
理那と名乗った女性は、微笑みを絶やさず、あくまで礼儀正しく言った。
「先生の治療、評判ですよ。丁寧で、正確で、なにより“手が信頼できる”って──私も、患者として体験してみたいくらいです」
リップサービスだろうか?
だが、その言葉にも妙な観察の匂いがあった。
「それで結局……ご用件はなんですか?」再び語気を強める。
「ええ、今回のフェスティバルに合わせて始まった<街のアップデート>について、先生のような専門家のご意見を伺いたくて」
彼女は、タブレット端末の画面を僕に見せた。
そこには、未来的なレイアウトで構成された施術ブースの図面と、そこに並ぶ施術体験モジュールの数々が映っている。
「これは…」
「次世代医療──AIによる感覚最適化治療です。人間が本来もっている不調の予兆を、AIが読み取り、最小限の刺激で快適さを維持する技術。 都市レベルでの運用はまだ珍しいですが、この街では先行導入が許可されました」
彼女はこともなげに言ったが、その言葉の中には、すでに後戻りできない流れを感じさせる確信があった。
「感覚…最適化…?」
「はい。苦痛の芽を摘み取るんです。気づかないうちにストレスを軽減し、必要なら記憶の調整も行います。 たとえば、疲労の記憶を軽く書き換えるだけで、患者さんの回復度は飛躍的に上がるんですよ」
言いながら、彼女は淡いブルーの光を発する小型のデバイスを取り出した。
指先ほどの大きさの球体が、微かに振動していた。
「それが?」
「体験用の端末です。ほんの一分で、視界と感情のバランスが整います。もちろん、手技療法と組み合わせて使うことも可能です」
僕は無言で、その球体を見つめていた。
たしかに雪野さんが言っていた。
「光が降ってくる感じでした。天井じゃなくて…目の内側にゆっくりと」
それは、彼女の感覚の中に入り込んでいた何かと酷似している。
「導入の対象に、私の院が含まれているということですか?」
「いえ、対象ではなく期待です。先生のような方が、この街の治療基準を支えてくだされば──私たちも、たいへん心強い」
とても優しい声だった。だがその言葉の裏には、明らかに選別の響きがあった。
僕は立ち上がり、カウンター越しに一歩近づいた。
「たとえば、人間の痛みを全部取り除いてしまったら…人は、何をもって自分の身体を知ればいいんですか」
理那は、少しだけ笑みを深くした。
「……それを問うことが、先生の限界です。身体を感じることに価値があると思い込んでいる。その価値観自体を変えるのが、これからの治療です」
答えのようでいて、なにも答えていない。
それでも彼女の言葉には、人を納得させてしまう妙な説得力があった。
「また改めて伺います。今日は、ほんの導入ですから」
そう言って、彼女は一礼し、受付の外へ出ていった。
ドアが閉まり、院内に静寂が戻る。
その静けさは、何か大きな音の前の静まり返った予兆のように感じられた。
僕はふと、指先を見つめた。
昼間、雪野さんの背中に触れたときと同じ感覚が、今も微かに残っていた。
◆
笹本理那が立ち去ったあと、しばらく院内は沈黙していた。
受付の照明が、白く無機質に揺れていた。
手のひらの温もりも、空気の気配も、ほんの少し異質に感じられる。
導入──あの女はそう言った。
まるで、この街そのものが一つの被験体であるかのように。
そっと窓を開けると、深夜の空気が静かに流れ込んできた。
どこか澱んでいるような、微かに熱を含んでいるような感触があった。
視線の先、広場の一角では、仄かに光る店舗群のシルエットが夜のなかに溶けていた。
数時間前にはなかったはずのブースが、またひとつ増えている。
まるで、眠っているあいだに風景ごと入れ替えられているような──
不気味な違和感が、じわじわと背筋を這い上がってくる。
と、僕のスマートフォンが、ほとんど音のしない通知音を鳴らした。
画面を見ると、そこには《ゆぅさん》の名があった。
既読を促すように、短いメッセージが点滅している。
【先生、少しお話できますか?明日の昼前、お時間いただけると助かります。】
──ゆぅさん。
17年間、ずっと共にやってきたスタッフであり、戦友であり、心の拠りどころでもある女性。
最近の彼女には、いつもと違う気配が滲んでいるような気がする。
どうして今夜、このタイミングで連絡を?悩み事でもあるのだろうか。
僕はスマホの画面を伏せ、再び広場を見つめた。
風が、少し強くなっていた。
街が音もなく、何かに呑み込まれていく気配が、夜の底からゆっくりと満ちていた。
(さすがに疲れたな…)
ウォーターベッドの刺激を受けながら横になると、間もなく意識が遠のいた。