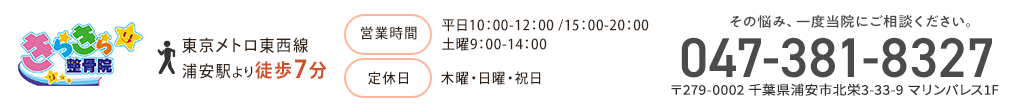小説「掌の記憶」第五章
― 潜入
取り戻す。絶対に。
頭の奥がしびれたみたいにじわっとしていて、熱に浮かされた様なのに、手足だけが異様に冷たい。
焦りも、怒りも、怖さもあったはずなのに、今はもう、それらを感じる余裕すらなかった。
僕は、治療院の物置部屋に駆け込み、棚の奥を開けた。
自宅に保管しておくべき、キャンプ道具の数々は移動に便利だからという理由でそこに収まっていた。
公私混同甚だしいのだが、今回はそれが幸いした。
まず手に取ったのは、薪を割るのに使っている刃の厚みがあるナイフ。
背をハンマーでたたいても傷一つつかない丈夫な品だ。
握りなれていた感触が手になじむ。
次に、軽量なLEDランタン。コンパクトだが光量は十分。
簡易バッテリーとセットでバックパックへ放り込む。
さらに、火起こし用のマグネシウム棒、小型の止血パッド、ホイッスル、登山用の薄手グローブ。
手際よく選別し、使い慣れた装備で最小限のサバイバルセットを構成した。
災害などの備えも考えて始めた登山やキャンプの趣味が、こんなところで活きてくるとは思いもよらなかった。
テーブルの上には、もう一つの道具―慎也から受け取った紙の地図があった。
「施設の中枢構造は定期的に改修されてるが、基礎構造はこの頃のままだ」
そう言って差し出されたそれは、行政がAI化される以前、旧施設時代の構造図だった。
厚手の紙に焼けたような折り目が残り、端にはボールペンで記された書き込みが点在する。
巡回を避けるためのタイミング、開錠されたままの点検口、使われていない非常階段。
もちろん古くて使えないものも沢山あるだろうが、内部に通じていなければ分からない情報が、実に正確に添えられていた。
慎也は学生時代、この施設の清掃バイトをしていた時期があった。
「どうせ暇つぶしだ」と笑っていたが、記憶力がよくて、建物の構造まで覚えてしまっていた。
これは、あの頃の記憶に基づいて補足されたものなのだろう。
最近付け足したような記述が混じっているのには違和感を覚えたが、これも彼の考えあってのことだろう。
(慎也…お前、本当に何でも知ってるな)
僕は地図を丁寧に折りたたみ、防水ケースに入れてポケットに滑り込ませた。
◆
夜も更け、人の気配が完全に消えた頃。
僕は中央広場の外縁を通り抜け、地図に示された裏手ルートへと足を向けた。
広場に併設された緑地帯を抜け、搬入車しか使わないメンテナンス用スロープに入る。
地図にある慎也のコメントどおり、監視カメラの視線が薄い整備用の通路を歩き、古い搬入扉へとたどり着いた。
目の前に現れたのは、くすんだ鉄扉。
今は全く使われていないようで、塗装はところどころ剥がれ、蝶番の隙間から錆が浮いている。
僕はナイフを取り出し、ラッチの隙間に差し込む。
呼吸を止め、慎重にこじる。
カチン―錆びた鋲が飛び、閂(かんぬき)が壊れる。
ゆっくりと鉄扉を押し開け、中へと滑り込むと、ひやりとした空気が肌を撫でた。
どこにも明かりらしいものはなく、闇が奥へと広がっている。
LEDランタンを最小光量で点灯した。
白く頼りない光が、無人の廊下を静かに照らした。
今では使われなくなった設備系の通路だが、書き込みのとおりセンサー類も死んでいるようだ。
コンクリートの壁に手を添えながら、僕は静かに進んだ。
息が少し荒い。けれど、不思議と足は止まらない。
眠気も、空腹も、まるで感じない。
この先に、彼女がいる。
それだけが今、僕の全身を突き動かしていた。
旧搬入路は、まるで打ち捨てられた洞穴のようだった。
配線は剥き出しのまま天井を這い、壁は湿気で黒ずみ、足元のタイルにはうっすらと苔が生えている。
不気味さと静けさ。
それでも、監視をすり抜けることより造作もなかった。
昼間の職員とのやり取りの方が、よほど緊張感があった。
やがて通路の先に、重々しい鋼鉄製の扉が現れる。
施設の正規ルートと繋がる、隔絶の境界。
(ここからが、本番か……)
也の手描きの地図には、この扉から先がAIの管理区域だと記されていた。
本来なら、認証や監視センサーが待ち構えているはず。
不審者の侵入を、そう簡単には許さないはずだった。
―けれど。
向こう側の照明の明かりが扉の隙間から漏れている。
(開いてる…のか?)
慎重に扉の取っ手に触れると、重厚そうな扉がウソみたいにあっけなく、音もなくスムーズに開いた。
警戒して周囲を見渡すが、センサーの作動音も、光も反応しない。
まるで、ついさっき何者かがここを通ったような気配。
そんな違和感が空気に残っていた。
化け物が出てくるわけでもないだろうが、やはり不気味には思えてしまう。
しかし、逆に考えればこんな幸運もそうそうないだろう。
いずれにしても、今は考えている暇はない。
僕は身を低くしながら、その白い光に満ちた内部空間へと足を踏み入れた。
◆
そこは、あまりにも整然としたフロアだった。
塵一つも許されない、病院でいうところの無菌室のような清潔感。
人工大理石のような白い床。壁も天井も白で統一され、余計なものは一切ない。
等間隔に案内灯が埋め込まれているが、照明は刺激にならないよう間接的に設計されている。
直線だけで構成された構造物は、まるで設計図をそのまま立体化したような美しい印象だった。
そして、まったく音がしない。
フロアに「吸われている」と考えてしまうくらいに靴音も、衣擦れも、呼吸音すら壁に吸収され、空間に残らない。
音響も反響も許さない、異様なまでに静かな静寂。
地図の記載にも『静寂』とだけ書かれて、二重線で囲まれていた。
(ここがD6区画で間違いなさそうだ)
その無機質な空間に、これでもかという衝撃を残している異物が、視界の端に映る。
血痕。
こんな跡を見るのは、生まれてから数回しかないのだが、見間違いではないだろう。
なんと言っても、僕は血を見るのがとても苦手だ。
映画やドラマでも、ちょっとリアルだったり、想像させられる場面では「血の気が引く」くらいだ。
さっきまでの冷静さはどこかに行ってしまったかのように、景色がグラッとなり、一瞬めまいが起きそうになる。
吐き気をこらえながら近づいてみると、足跡のような間隔で奥へと続いている。
(まさか、これって…ゆぅさん!!)
心臓が跳ねる。喉が詰まりそうになる。
傷を負って、こんな場所まで?
搬送の途中で何かトラブルが起きたのか?
ランタンを強く握りしめた掌は汗で濡れている。
無音の空間で、自分の心臓の音だけが、やけに響いていた。
答えは、血痕の先にある。
はやる気持ちを抑えきれず、白く静かな廊下を早足に進んだ。
◆
血痕は、廊下の端―奥の区画へとつながる電子ロック扉にたどり着いた。
先ほどの扉と同様に重厚そうな扉だった。
全く違っていたのは、どこのだれが見てもその扉は
「開いている」
壁には、暗証入力や生体認証といったセキュリティが用意されていたであろう操作パネルが設置されていたが、今は緑のランプが一つ付いているだけで、ここを通過しても何の問題も無さそうに見える。
しかし、扉の向こう側に広がっている景色が、この区画とは比べられないくらいアナログ感満載だった。
金属と機械油、そして古い薬品の匂いが混ざり合ったような、重たい空気。
思わず鼻で息をするのを避け、口を結び直す。
D6区画とは、まるで別世界だった。
天井には、艶のない保護被膜に覆われた無数のパイプとコードが這い、そこから伸びた一部が壁を這って床まで降りている。
蛍光灯のいくつかは切れかけているのか明滅を繰り返し、パネルの警告灯が点滅しているせいで、空間全体が不穏な赤色を帯びている。
お化け屋敷の照明効果のように、まるで生き物の触手のように、パイプやらがうごめいているようにも見えた。
先の区画とは対照的に、いくつあるのかもわからない機器類の冷却ファンが連続的に唸っていた。
そして部屋には端末、無数のケーブルポート、昇降台、診断椅子などが設置されており、旧時代的ではありながらも、当時の最新テクノロジーが詰め込まれたような絵に描いたような「研究所」の様相を呈していた。
自身にははっきりと説明のできるような知識はない。
しかし、机に乱雑に散らかっている書類などからも、以前からここでAIに関わる研究がおこなわれていたことは、火を見るよりも明らかだった。
赤色の光に目が慣れてきたのか、部屋を少し奥に進んだ角に人の背丈ほどの卵型の影があることに気が付いた。
ランタンの明かりで照らすと、ケーブルや配管が壁の四方から床を這って集まっている『巣』のような構造体。
その中央、無機物に使うには不思議な表現だが、ふんわりと抱き留められているかのように彼女はいた。
「……っ……」
声にならなかった。喉がひきつって、息が止まる。
…ゆぅ…さん
いつも彼女が着ていた白衣のまま、身を預けるようにして座っていた。
目を閉じていて、微動だにしない。
表情はうまくつかめず、眠っているようにも、意識を失っているようにも見えた。
コードの数本は、彼女の後頭部や背中の方から生えている様にも錯覚させられる構図だった。
いや、実際に接続されていてもおかしくはない。
「…ゆ、う…さん…」
脚が震える。
ふらふらと一歩を踏み出す。
「ゆぅさん……っ!ゆぅさんっ…!」
喉から搾り出した声は、あまりに情けなく、掠れていた。
1分前までは、そろりと物音を立てないように忍んでいたはずなのに、急激に高まる気持ちを抑えきれなかった。
視界が歪む。滲む。足元が揺れて、床と距離感がわからない。
「見つけた…見つけたよっ!」
迷子が母を見つけて、声を上げるように叫びをあげる。
涙が頬を伝い、口元を濡らした。
泣きながら、叫びながら、彼女の元へと駆け寄った。
情けないくらいに取り乱した姿だった。
もちろん、そんなことは構いやしない。
―この瞬間を願っていた。
どこかに潜んでいた最悪の『覚悟』が想定外だったことに安堵した。
震える手で、彼女の肩にそっと触れる。
部屋の温度のせいか随分と冷たくは感じる。
でも、生命の温もりを失ったそれではないと直感でわかった。
「ゆぅさん」
頭に衝撃を与えないよう気遣いながらも、声を張り、呼び起こすように少し揺さぶってみる。
ぴくっと、手から筋肉の収縮に触れた。
「…先…生…」
呟きながら、やや機械的にゆっくりと瞼が開いていく。
焦点の定まらない瞳が、こちらをさまよい―やがて、僕をとらえた。
「…ほんとに…先生…?」
「…うん。僕だよ。大丈夫、もう大丈夫だから…」言いながら、手を握る。
その手も冷たかったが、ちゃんと僕の手を握り返してきた。
「…来てくれたんだ…ごめん…なさい…」
その一言に、胸が張り裂けそうになる。
謝る必要なんて、どこにもないのに。
「そんなこと…言わないで。謝るのは僕のほうだ…っ」
ゆぅさんは、優しく微笑んだ。
でも―どこか遠い。
夢の中で見る笑顔みたいに、ふわふわとして定まっていない。
「先生、わたしもね…、助けたかったの」
ぽつり、ぽつりと話し始めた言葉は、やがて堰を切ったようにこぼれ始める。
「かんじゃさんの…痛いの…つらい…の、どんなに話を聞いてあげても、私では届かなくて…。でんきをどこにつけてあげたら、もっと楽になるかな…とか、工夫したりしたんだけど…。わたし…先生じゃ…ないから…」
「うん…うん」
「もうちょっとこうしたら、とか思いながら…帰っていく背中を、毎回…見送ってたの…」
僕は、言葉を飲み込んだ。
「…AIの治療は…精密で…誰にでも扱えて…命にすら届く技術だって…。わたし…も、それなら…みんなの笑顔…取り戻せる…って…」
彼女の目の焦点がぼやけはじめ、言葉のリズムも不自然になっていく。
「で…も…違った…簡単じゃ…なかった…混ざるとね…。どこ…まで…自分なのか……わからなく…」
声の抑揚、表情、言葉の間合い――すべて機械的になっていくような恐ろしさがあった。
「わ…たし……まだ…ココニ…イル? ちゃん…と…ワタシ…デ…ス…カ?」
そう問いかけてくる彼女の手は、小さく震えていた。
「いるよ…っ、いるに決まってるだろ!」
僕は強く、手を握り返した。
「大丈夫、ゆぅさん…!大丈夫だから…わかってる……全部わかってるから!」
視界がにじんで輪郭が曖昧になっていく。
「君は…ずっと人のことばかり考えて、自分の痛みも飲み込んで…なのに、こんなっ!」
彼女は静かに目を閉じた。涙を浮かべたまま、唇がかすかに動く。
「……先…生…アリがトウ…。もうスグ……わタシ、ナニカニ…なるヨ…ォ…」
「ならせない!させるもんか!」
腕の力に、思わず力が入った。
「絶対に…連れ戻すから!一緒に帰ろ…う」
「うん。…それ、いいな」
一瞬目を開けて、本来の彼女らしい相槌を打つと、大きく息を吸い込み、そして再び目を閉じた。
(まだ、間に合う)
僕はその手を、胸に抱きしめた。
この命を、離さないと誓いながら。
◆
ギキイィィィィィッ
と、突如響く金属音に、僕は反射的に振り向き身構えた。
部屋の最奥部、暗がりの中から崩れ落ちるように、女が姿を現した。
「こっちには…来ないで…」
「さ…笹本?」僕は言葉を噛みながら、目を細めた。
間違いない。ゆぅさんを連れ去った女。
怒りが一気に噴き上がるが、同時に彼女の足元に広がる血だまりが目に入る。
前の区画でも目にしていた血痕の主は彼女だったのだ。
太腿の付け根―大腿動脈。
そこから流れ出る血は、何もせずとも命が尽きるほどに深く、赤かった。
「なにがあった?」
問い詰めるように言ったが、感情がまったく整理できない。
「そんなこと…どうでもいいの…」
かぶりを振った彼女の唇は白く、震えていた。
どこか必死に理性をつなぎとめるような目で、こちらを見つめてくる。
「早く…しないと。彼女が『融合』の最終段階に入る」
「融合?どういうことだ」
「人とAIの完全同調。思考、感情、記憶…を接続し、制御する。彼女は…その実験の成功例よ」
現実味のない言葉が続く。
だが、命の危機を迎えている彼女の声には一分の嘘もなかった。
「フェスティバルは…街中の住民に、AIとの感情リンクを試験的に施す場だった。全体を操作する中枢として、より同調した人物が必要だった…ここの住民にも愛されていた彼女は、適役として選ばれたの」
怒りで、握った拳が震える。
しかし、今はそれよりも―
「助けられるんだな!方法は?」
「左手の壁…配線の裏に端末がある。このコードを打ち込んで…」
笹本は、血に濡れた手で、懐から紙片を差し出した。
そこにはアルファベットと数字の列が、崩れた筆跡で記されている。
「これで接続は遮断される。融合は止まる…ただ…」
「ただ、なんだ?」
「AIとリンクしてる住民の心が…遮断の影響で、壊れる可能性があるの」
苦しそうに一回呼吸をし、そして付け加える。
「記憶の断絶、感情の崩壊、自己認識の消失…一部の人は”心の死”を迎えることになるかもしれない」
「かもしれない?」
「確実じゃない。でも、起きても不思議じゃない」
僕は息を詰めた。
ゆぅさんを救えば、街が壊れる。街を守れば、ゆぅさんが―
「なぜ…こんな」
呻くように問うと、笹本は遠い目で、かすかに笑った。
「悲しむ人が、いない世界を…信じてたの。誰も傷つかず、誰も苦しまない。完璧なバランスで、人も心も、整えられる…そんな未来を」
言葉を絞り出すように、笹本は天井を仰いだ。
血に濡れた頬を、涙が一筋伝う。
「それが……私の……りそう……」
その声は、どこか幼くて、頼りなくて―
「……おかあ……さ……ん……」
最後の一言がこぼれ落ちた瞬間、彼女の首がかくんと垂れた。