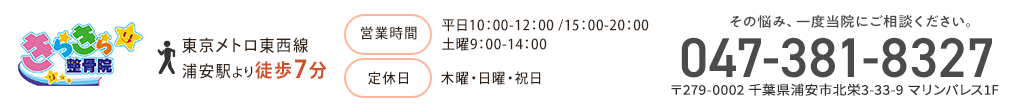小説「掌の記憶」第六章
― 心の器
しばしの沈黙。
D7区画の片隅でこと切れた笹本に、そっと白衣を脱いでかけた。
血に濡れた衣服の上からでも、その表情はどこか穏やかで、呪縛から解き放たれたようだった。
やり方は間違っていたとしても、自分の信念のために命を賭けた結果なのだろう。
その矛先が違ってしまっただけで、本当は同じ場所を目指していたのかもしれない。
餞(はなむけ)にもならないが―
この白衣が彼女の正義に対するリスペクトの証明になることを願って。
配管の奥で低く唸る空調の音に混じって、
か細く、かすれた声がした。
「先生…」
はっとして振り返ると、配線に包まれるようにして座っていたゆぅさんが、わずかに目を開けていた。
「ありがとう…ございます」
その声に、僕は何も言えなかった。
「私…嬉しかったんです、本当に。」
「開業しようって、先生が決めた時…何の迷いもなく、私に声をかけてくれたこと…あの時のこと、今でも覚えてます」
胸の奥がじんわりと熱くなる。
(ああ、懐かしいな)
「毎日、いろんな人が来てくれて、先生の施術が終わると、笑顔になって帰っていって…その横で、私も…いつも誇らしかったですよ」
「ゆぅさん…」
溢れ出る想いは言葉にならず、ただ彼女の名を呼ぶだけだった。
こんな会話をして、懐かしがっている場合ではない。
そう分かっているはずなのに、耳が彼女の言葉を拾ってしまう。
(早くコードを入力しないと)
でも…脚が、カラダが動かない。
彼女とこうして話すのは、これで最期になるかもしれない。
頭の片隅で否定しながら、そんな風に考えしまう自分がいるのがわかる。
(冗談じゃない)
心とカラダの葛藤を見透かしたように、彼女が語りかける。
「先生…もう大丈夫…」
「…私ずっと頑張ってきたから…ちょっと疲れました」
(そんな言い方はやめてくれ)
「ああ…」
返事にもならない言葉を返しながら、僕はたちあがって操作盤に向かおうとした。
ピピピピッッ!!
その時、耳障りな警告音が鳴り響いた。
「…あぁ…わ、わたし…かワって……シま……う……」
空を見つめる彼女の瞳は、光を失い、焦点はどこか遠くを彷徨っている。
(迷うのはもう終わりだ)
端末の前に立ち尽くし、震える指先でコードを打ち込んでいく。
文字列の最後―あと一つだ。
これを入力すれば、すべてが終わる。
(終わるのか?)
いいや、違う。
これは、ゆぅさんを「救う」という選択の始まりになる。
しかし…
「それをした結果、住民がどうなるのか、あなたはわかっている?」
「AI接続中の人々は、心の死を迎えることになる…かもしれない」
脳裏に、笹本のあの言葉が蘇る。
かもしれない、だと。
たったそれだけの、不確かな未来。
その“かも”が、指を止めさせる。
今、すぐに助けたかった。
彼女を失いたくない…
なのに、これまで触れ合い、寄り添って来た街の人たちの姿が脳裏をよぎる。
救うために、切り捨てる。
医療に携わりながらも、その残酷な側面は僕の業には皆無だ。
命に関わるリスクもない。
これまでの自分がとても小さく、惨めに思える。
(いや、そんな理屈…今、要らないだろ)
混乱してクラクラする頭を少しでも正常にしたくて、酷く汗ばんだ額に手をやり、両方のこめかみを指圧する。
その時、画面に浮かんだ接続深度の数字が変わった。
――97%
脳が痺れる。
(もう…考えられないっ!)
慌てて、最後のナンバーを押す。
――98%
「…っ、頼む、間に合って!!」
エンターキーを叩いた瞬間、部屋の照明がわずかに色調を変える。
続いてケーブルの光が消え、接続端末から空気が抜けるような音が鳴った。
周囲の機械音は、一段階トーンを落とし静寂が戻ってくる。
ディスプレイには、「接続中断」の表示。
どの数字はもう動いていない。
全身が痙攣してるみたいに震えている。
間違ってまたキーを触らないように、手を下におろしながら、ゆっくりとゆぅさんの方へと振り返る。
彼女は元の場所にいたが、接続されていたケーブルが外れたせいなのか、そばのパイプに寄りかかるように横たわっていた。
躓きそうになりながら、彼女のもとへ駆け寄る。
目は、閉じたまま。
でも、ケーブルが接続されてない様子は、呪縛から解放されたようにも映る。
「ゆぅさん?」
返事はない。
そっと首筋に指をあてて、脈診する。
(大丈夫だ)
安静時にしてはやや速いが、それでも生命力を感じる強さで脈打っている。
頭に衝撃がいかないよう注意しながら、一度抱え起こすようにして、隣の診療台に横たわらせる。
穏やかに胸が上下するのも確認できた。
「間に合った」
誰に報告するわけでも無いが、声を張って口に出したことで、現実味が増した。
声を聞きつけて誰か来るのではと、耳をすませたが、横たわる彼女の呼吸音だけが、かすかに響いていた。
身体にも精神にも負荷を受けているはずだから、このまま少し休めて彼女の回復を待とう。
焦って無理に動かすのはダメだと施術者としての勘が言っている。
とかなら格好良いのだが、もう限界だ。
自分はエージェントでも戦士でもない。
普段、身体を動かしているとは言え、不眠不休でここまで動くのは、明らかにオーバーワークだ。
震える膝をつき、僕は彼女の横たわるベッドのそばに腰を下ろした…つもりだったが、冷たい床の感触を頬に感じながら、意識が遠のいていくのがわかった。
……
仮装パーティーに、射的、かくし芸。
ゆぅさんは、担当している受付の飾り付けを張り切りすぎて、風船で埋まりかけている。
それを見て「やりすぎじゃないか?」と笑っているのは慎也だ。
つられてスタッフも、患者さんも、みんな笑ってる。
これは、夢だ。
ー開業記念日のイベント。
「この方が、絶対可愛いでしょ?」
彼女の笑顔が鮮やかに蘇る。
決して強い調子では無いのに、チカラを感じるキッパリとした物言いは、時に迷ってる人を支え、勇気づけた。
開業する時に、僕を誰よりも後押ししてくれたのも彼女だったな。
人と人とが行き交い、関わり合って、笑い合って、泣き合って、支え合って。
それな毎日は、凄くきらきらしていた。
ーAIなんて要らなかった。
……
ハッとして目を覚ます。
一瞬、思考が止まったが、パイプだらけの天井を仰いで、全ての現実を思い起こす。
どのくらい時間が、流れたのか。
上半身を起こし、確認する。
カウントダウンを止めてから、1時間ほどが経っていた。
ゆぅさんは、まだ眠っているようだ。
いつ、目を覚ますのだろうか?
専門家もいないこんな場所で、この後どうすればいい?
がむしゃらな行動の末路に、急な不安が押し寄せる。
「まさか、間に合ってないとか?」
その言葉が唇から漏れた瞬間、僕の胸を突くように鈍く痛みが走る。
誰からも正解がもらえない問いに、頭がグルグルして目が回る。
急な眩暈に吐き気をおさえる…
とその時、
頭上の診療台から伸びた彼女の手が、座っていた僕の頭にそっと置かれた。
「よく頑張りましたね」と労うように。
胸が熱くなる。
涙が滲んでくる。
僕はその手に、そっと自分の手を添えた。
今はこれだけでいい。
少なくとも彼女は、生きてくれている。
「…帰ろう」
声に出して、つぶやく。
「帰ろう、僕たちのきらきらに」